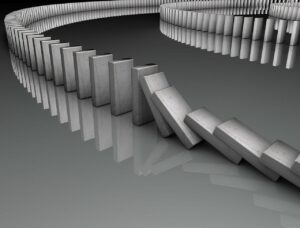※本原稿は、Business Journal2015年2月24日号に掲載されました。
あなたは、こんな企業をどう思うだろうか。社員が休み時間もなく夜遅くまで働き、必要とあらば土日も出社し、残業代がすべて支給されるわけではない。経営理念を社員全員が覚え、社長が示す将来ビジョンに誰も文句を言わない。「間違いなくブラック企業だ」と思う読者も多いのではないだろうか。しかし、それは大きな間違いである。一方的な見方にすぎないのだ。
年中ガムシャラに働きながらも、社員の目がキラキラ光っている会社がある。労働量から見ればブラック企業に引けを取らないのに、社員はモチベーションが高く、企業に貢献することを惜しまない。「ブラック企業」という言葉がある一方、このように社員がイキイキと働く企業を表すワードが見つからないのも不思議である。
今年の2月に発売され話題となっている書籍『実践ワーク・ライフ・ハピネス2』(監修:藤原直哉著者:阿部重利、榎本恵一/万来舎刊)では、社員が働くことを楽しんでいる企業を「ハピネスな会社」と定義している。筆者はこの定義が最も適していると考える。
筆者はこれまで多くの企業を取材してきたが、その中にはまさに「ハピネスな会社」があった一方、その真逆な「ブラックな会社」も多くあった。その違いはなんだったのか。事例を挙げながら述べてみたい。
「ハピネスな会社」を体現するベンチャー企業
ここで紹介するのは、某ベンチャー企業である。2005年当時、社員80名だったこの企業は、上場も目指せるほど勢いよく業績が伸びていた。筆者が社員に取材したところ、誰からも同じような答えが返ってきた。「当社の社員は、みんな幸せです。会社の悪口を言う人を聞いたことがありません」
まさかそんな会社があるわけない、社員はそう言わされているだけだろう、と筆者は疑問に思い、しばらく会社を取材し続けたが、社員は本音を語っていることがわかった。まさに「ハピネスな会社」だったのだ。
この会社の特徴は、なんといってもカリスマ性のある創業社長にあった。社長は毎日のように未来の夢を語り、その言葉に社員全員が魅了されていた。社長自ら営業に動き、社内のどの営業マンよりも大型の契約を取り、大きな夢が実現することを証明していた。「そのうちに(大企業の)○○社と一緒に仕事をすることになる」などと大風呂敷を広げては、それを次々に実現していた。幹部社員も社長の夢を継承すべく、いつも部下に会社が目指す夢を語っていた。「日本から世界へ飛び出し、この分野で世界一の会社となる」という社長の夢に共感し、社員全員がその夢に向かってガムシャラに働いていたのだ。
社員の自主性を重んじ、提案する企画を歓迎して予算も与え、利益が出れば社員全員にフェアに分配した。社員のプライベートも充実させるために「日本一給料が高く、日本一休みの取れる会社」を目指し、それを実現しつつあった。年に一回の社員旅行にも全社員が参加し、社長とともに時間を過ごすことを楽しんでいた。社長が社員に愛され、社長も社員を愛していた。
「ハピネスな会社」がブラック化する
しかし、わずか数年で、「ハピネスな会社」が「ブラックな会社」に転落することになる。社長が難病にかかり病気療養を理由に退任し、株主も変わった。株主から送られた新社長は辣腕経営コンサルタントだった。新社長は就任するなり全社員を集め、こう宣言した。
「ビジネスは数字だ。数字こそ結果だ。前社長はいつも夢のようなことばかり言っていたようだが、私は数字の裏付けのないことは信じない。新しい経営手法を導入し、改革を行う」
経営コンサルタントの新社長から見たら、「なんと曖昧なことで動いている会社だろう」と感じたに違いない。新社長は業務管理やプロジェクト管理、営業管理に最新ITを使ったシステムを導入し、そのシステムによって個人の評価がポイント計算されるようにした。
新社長はこれを「見える化革命」と呼んでいたが、社員からは数字による管理が始まったとしか思えなかった。新社長は夢を語ったり、大風呂敷を広げることもなかった。売り上げ目標を明確にし、それをどこまで達成したかを重要視し、社員には個別に目標数値を与えて叱咤激励していた。目標達成にほど遠い場合、「結果を出すのがプロだ。残業してでも達成しろ」とプレッシャーを与え続けた。
「まったく別の会社になってしまった」と社員が嘆くようになり、優秀な社員から会社を辞め始めた。残った人は、「会社に魂を売った」と揶揄されるほどだった。目をキラキラさせていた社員はもういない。数字に追われて鬱病になる社員も出てくるようになった。中には過労で亡くなった人もいる。もはや、どこからどうみても「ブラックな会社」である。
今では全盛期の3分の1まで売り上げが落ち、社長もクビになり、会社はますます迷走している。夢に満ちた会社は、事実上もう消えてしまった。
「ハピネスな会社」と「ブラック企業」の違い
この天国と地獄を経験した会社の事例をみれば、「ハピネスな会社」には何が必要かわかるだろう。筆者は次の3つの要件が最低限必要だと断言する。
(1)社長が魅力あるビジョンを語り続ける
社員は、「なぜこの社長のもとで働かなくてはならないのだろう」と思いながら働くものである。つまり理由が欲しいのだ。「生きるために働く」という時代はすでに過ぎ去り、“働き甲斐”を求めているのが現在の人たちだ。マズローの欲求5段階説を持ち出すまでもなく、成熟した社会では、お金だけでなく自己実現や社会貢献のために働くことに人々はモチベーションを感じるものである。
人間本来持っている欲求を満たしてあげることは、企業トップの重要な役割である。社長が示すビジョン・夢・理念が魅力的であればあるほど、働き甲斐のある会社風土が醸成されていく。
(2)社長自らビジョンを実現させてみせる
ソフトバンクの孫正義社長は昔から「大ぼら吹き」と言われている。言葉を換えれば「大きな夢を語ってきた人」といえる。しかし「大ぼら吹き」はどこにでもいる。孫社長が、その他大勢の「大ぼら吹き」と違うのは、それを実現してみせたからである。
夢を語りながら、それを社員に押しつけようとするのは虫のいい話である。そんな態度の社長は社員にすぐに見抜かれてしまう。社長自ら動き、夢を形にさせて初めて、社員は社長の言葉を信じるようになる。夢を語るだけで社員がついてくるはずがない。
社長の語るビジョンが現実になることがわかれば、社員はその会社で働くことが夢の実現につながると必然的に感じるようになる。余計なモチベーションアップの仕組みを導入するより、はるかに効果的である。社長は常に背中から見られていると心得るべきである。
(3)社員の自主性を重んじ、自由度を広げる
人は管理されればされるほど、能力を発揮できなくなる。以前、タイムマネジメントの手法として全国の企業で導入された画期的システムがあった。社員の生産性を最大限に上げるために、分単位で行動を管理し、より生産性が上がる仕事に時間を配分させる仕組みだった。中小企業から大企業まで導入されたが、真剣に導入した企業ほど業績が悪化していった。論理的には生産性が上がるはずだったが、現実には真逆の結果が出たのだ。
その理由は、あまりにも当たり前のことだった。人間はロボットではない、ということだ。ロボットならプログラムされた仕事を、いつでも均一に実行することができるだろう。しかし人間はそうではない。調子の良いときもあれば悪いときもある。いわゆるバイオリズムがあるのが人間だ。時間管理を厳格に行い、無駄のない仕事配分を行ったとして、そのプログラム通りに実行できないのが人間なのである。逆に厳格に管理されることでストレスを発生させ、生産性も低下してしまう。行きすぎれば病気にもなる。
その理由は、あまりにも当たり前のことだった。人間はロボットではない、ということだ。ロボットならプログラムされた仕事を、いつでも均一に実行することができるだろう。しかし人間はそうではない。調子の良いときもあれば悪いときもある。いわゆるバイオリズムがあるのが人間だ。時間管理を厳格に行い、無駄のない仕事配分を行ったとして、そのプログラム通りに実行できないのが人間なのである。逆に厳格に管理されることでストレスを発生させ、生産性も低下してしまう。行きすぎれば病気にもなる。
最新の行動科学の結論では、人は自主性を重んじられ、自由度が大きいと感じたときに最も生産性が高くなるということがわかっている。それは金銭的な報酬よりも大きいといわれる。「これを達成すれば○○万円もらえる」といわれるよりも、自主性と自由を与えられたほうが、人はモチベーションが高まるのだ。
この3つの要件を満たした企業は、「ハピネスな会社」になる条件が整ったといえるだろう。ここで筆者が「条件が整った」というのには理由がある。3つの要件は「必要条件」だが「十分条件」ではないからだ。
「ハピネスな会社」は結果ではなく、状態である。常に維持しなければ「ハピネス」でなくなってしまうからだ。先の事例で挙げた企業のように、同じ会社なのに、トップが変わるだけで「ハピネス」から「ブラック」に転がり落ちることもあるのだ。「ハピネスな会社」には、それを維持させているだけの優秀な社長の存在がある。それだけトップの役割が大きいといえる。
社員の幸福を最優先にし、業績を伸ばしている企業
前出の『実践ワーク・ライフ・ハピネス2』に登場する「ハピネスな会社」の5社の事例の中から、ユニークな会社を1社紹介しよう。
静岡県掛川市にリツアンSTC(以下、リツアン)という技術系人材派遣会社がある。リツアンの野中久彰社長は、派遣業界のブラックボックスといわれた手数料をオープンにしてしまった“革命児”だ。
もともと大手派遣会社で働いていた野中社長は、クライアント企業から得る派遣料から派遣会社が4割も5割もピンハネして派遣社員に給料を支払っている現実に憤りを覚えたのだ。
「派遣社員を安い給料で雇い、高い派遣料で売れ」
「利益率を上げろ」
こんな会話が当たり前で、一度たりとも派遣社員の幸福について語られることはなかったという。そこで野中社長は、派遣社員がもっと豊かに幸せになれる理想の派遣会社をつくるべくリツアンを創業した。
大手派遣会社の手数料平均は約38%で、多いところでは40~50%ともいわれるが、リツアンは23%と極めて低く設定し、しかもそれを公開にした。派遣会社では異例のことである。さらに派遣先から支払われるお金と、派遣社員が受け取る給料も開示し、創業の理念を嘘偽りなく貫いていることを明らかにしている。
野中社長は、各地に派遣されている派遣社員たちに会いに行くのが好きだという。「飲みニケーション」を頻繁に行い、会社の理念や夢を語ったり、派遣社員の課題も共有する。これにより、理想の会社を一緒に成長させているという一体感が生まれるのだ。
派遣先企業が派遣社員を引き抜いて正社員にすることはタブーだが、野中社長は逆に正社員になることを奨励している。「20代、30代なら派遣先はいくらでもありますが、60代になったら派遣先はないと考えたほうがいい。だから派遣社員の将来を考えると、正社員になったほうがいいのです」と野中社長は言う。リツアンの売り上げが一時的に落ちたとしても、派遣社員の幸福を優先しているのだ。
リツアンの派遣社員は、誰もが「働くのが楽しい」と語っている。会社が自分たちの幸福を第一に考え、給料面でもどこよりも優遇してくれている。そんなリツアンを、派遣社員自らあちこちで「とてもいい会社だよ」と自然に“宣伝”してくれるので、良い人材が集まってきているという。
リツアンの経営理念は「会社の発展と従業員の生活の向上が比例する会社」である。創業当時から掲げた理念を、野中社長は行動によって示している。だからこそ、社員がイキイキと働く「ハピネスな会社」になったのだ。
リツアンは創業からわずか8年で派遣した社員数が200人を超え、売り上げも10億円の大台を突破した。取引先も、NEC、ソフトバンクモバイル、日産自動車、ヤマハなど、大手企業がずらりと並ぶ。この成功は、理想のビジョンを掲げ、それを実現すべくタブーを乗り越えてきた野中社長の強い思いと社員への愛があったからこそである。
会社をハピネスにするかブラックにするか、それは社長次第である。時代を超えて変わらないこの原則を、今こそ見直すべき時ではないだろうか。